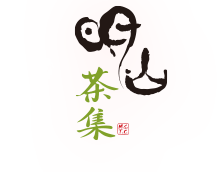明山茶集ブランドストーリー
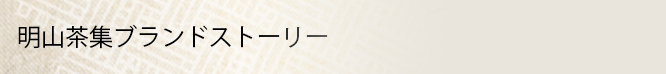

明山茶集ブランドストーリー
育てる、作る、売る。家業が四代続く。
沸く、淹れる、味わう。お茶の香りがシンプル。
経験に踏まえ、お茶を組み合わせ、
できたお味は季節を問わず、いつでも楽しめる。
一口啜って、生活の一味を感じる。
明山茶集ブランドストーリー
評茶台にずらりと並ぶ茶碗に様々な茶葉が広がり、色加減が違う茶の湯を見せている。放課後、遊びに急いでいる男の子が店内を通る都度、いつも父親に止められ、「これ、香りどうだい?じゃ、それは?」とお茶を味見した後の感想を聞かれている。こんな生活の中に密着したひとシーンが、正にお茶職人の育成教育の始まりである。

栽培から販売まで、四代にわたる関わりを持つお茶
曾祖父から父親の代までがずっとお茶の栽培に携わる農民であり、昔の頃、よくお茶を担ぎながら、新店の山奥から市内の大稻埕まで歩くものだ。当時の台北は、まだ台湾茶の加工と卸売の中心になりつつある所であった。その追い風に乗ろうと、三代目の父親は、祖父と大稻埕で「明山」を立ち上げ、お茶の加工と販売にも手をつけ、主にタイ、香港、日本へ輸出した。
出荷の締め切りに追われながら必死に頑張る父親が、乗り切った後によく娘たちを製茶工場に遊びに連れていった。「落ちていた茶葉の欠けらと溢れる香りは小さい頃の記憶なのだ」と姉は言う。働く時間が長いが、帰宅時間が午前様になっても、けっして娘たちの誕生日を祝うことを忘れない。そんな父親は、製茶工場にあるたくさんの機械の稼働音により、聴覚が日に日に衰えてきて、さらに肩と背中も100斤(1斤=600g)もある茶葉の重荷で、形が崩れてきていた。
末っ子の高煜程が生まれた頃、丁度台湾茶輸出のピークを迎えるところだった。哲学学科卒の高煜程は、進路に困り果てるところ、「哲学を学んで何でもやれるよ」と教授に励まされたので、先行きの可能性に気づくことができた。そこから、姉たちと手を組み、家業であるお茶取引に取り組むことにした。そこで、四代目の経営が始まった。
輸出から国内向け取引まで、良質安価へのこだわりが明山長年の経営方針だ。姉とこの伝統を守りつつ、高煜程は独自のブランドを創ることを決意した。彼はフランス小説『優雅なハリネズミ』での一言を認めた。「最小限の支出で楽しめる茶道を通して、誰でも心が癒され、センスが貴族並みになることも可能だ。なぜなのか。それはお茶はリッチな人とプアな人の飲み物なのだ。」安さは質を守ることへの挑戦であり、価格差が大きいという多様な茶飲料市場で、ほかに良いお茶に接触する手はないか、と彼は考え続ける